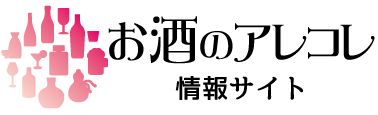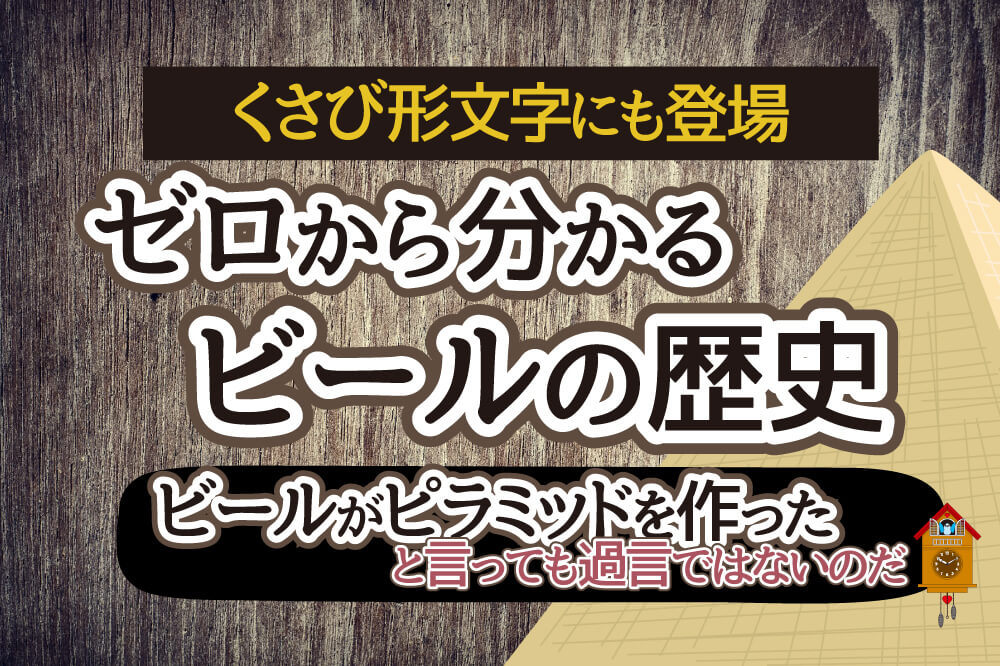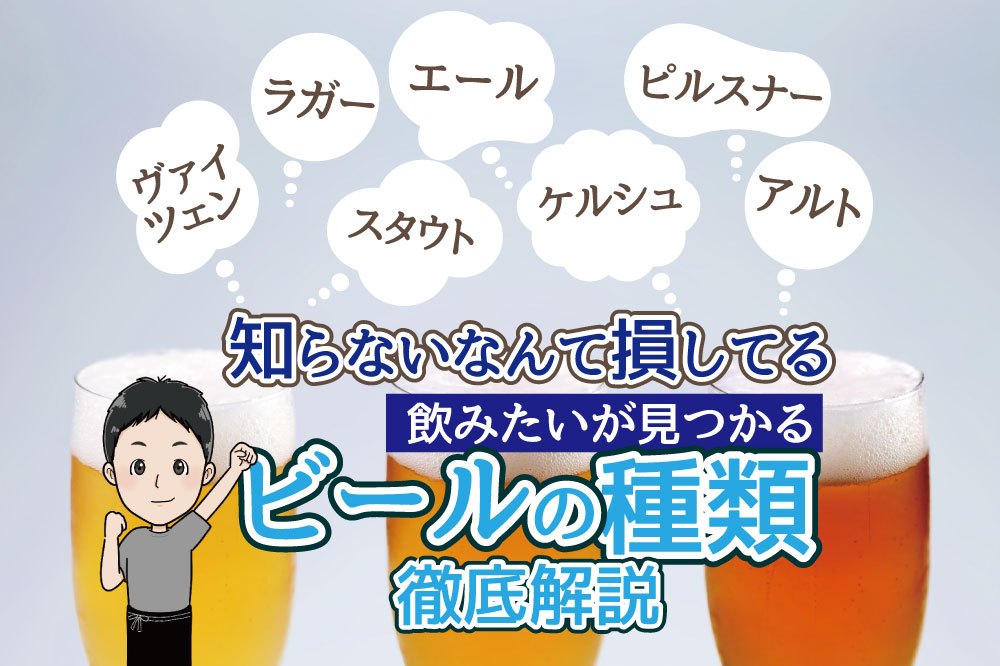
仕事終わりに飲むビールは、普段飲むそれとは違って、格段に美味しいですよね。中には、「このビールを飲むために生きている!」という人もいるほど、1日の締めくくりにぴったり。「明日も頑張ろう」という活力になります。
最近では、大手ビールメーカー4社が販売しているビールや発泡酒、第3のビールだけでなく、全国各地のブルワリーが手がけるクラフトビールをスーパーで見る機会が増えてきました。「たまには違うビールも挑戦してみよう!」と思って手に取ってみたものの、「いつものビールと何が違うのか分からない」そう思う人も多いはず。
今回の記事では、その違いを大解明!ビールの定義をはじめ、日本のクラフトビールの種類をたっぷりをご紹介します。毎日同じビールを選ぶのではなく、たまにはクラフトビールも味わって、その違いを楽しんでみてくださいね!
ビールの定義

ビールの歴史は古く、世界中の多くの人に愛される飲み物です。世界各地の飲酒人口も多く、いろいろな飲み方で世界中の人が楽しんでします。
一方でスーパーのお酒売り場に行くと、ズラリと並べられている缶ビールの数々。今日はどのビールにしようかな、なんてウキウキしながら購入したものが、ラベルを見ると「発泡酒」だった…そんな経験はありませんか?
実はこれ、日本の法律で定められたビールの定義が原因によるもの。国税庁が定める日本の酒税法第3条第12号では、ビールを次のように定義しています。
『次に掲げる酒類でアルコール分が20度未満のものをいう。
イ.麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの。
ロ.麦芽、ホップ、水、麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類又はカラメルを原料として発酵させたもの(その原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の100分の50以上のものであり、かつ、その原料中米以下の物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の5を超えないものに限る。)』
ややこしいですが、わかりやすく言い換えると、アルコール度数が20度未満かつ、麦芽比率が全体の50%以上、それ以外の原料が麦芽の重量の5%の範囲内のものが日本における「ビール」、この定義から外れたものは「発泡酒」や「第3のビール」になるのです。
このあたりのビールの原料を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
2018年4月に酒税法が改正されるまでは、ビール以外の原料を使用した場合(=副原料という)、「発泡酒」と表記しなければなりませんでした。例えば、キリンビールの「一番搾り」にレモン果汁1滴や香りづけのスパイスを入れただけで、それは「発泡酒」です。
しかし、酒税法の改正により、副原料が麦芽の重量5%までなら、「ビール」と表記できるように。今では、風味づけ程度にオレンジピールやコリアンダーを使用した飲料も「ビール」として認められています。
日本の酒税法によるビールの種類

上記でも説明した通り、国税庁が定めるビールの定義は
- アルコール分が20度未満
- 麦芽比率が全体の50%以上
- 副原料が麦芽重量の5%以内
でしたね。それ以外は、「発泡酒」や「第3のビール」に分類されます。
では、それ以外に分類される「発泡酒」や「第3のビール」の違いはなんでしょうか?テレビCMで見かける「麦とホップ」や「のどごし生」、「本麒麟」は、どちらに分類されるのでしょう?詳しく解説していきます。
実は、先ほど提示した「麦とホップ」や「のどごし生」、「本麒麟」は全て「第三のビール(新ジャンル)」に該当します。「発泡酒だと思ってた!」という方も多いでしょう。
それもそのはず。現在発売されている発泡酒は、「アサヒスタイルフリー」「アサヒ本生ドラフト」「アサヒ本生アクアブルー」「北海道生搾り」「極ゼロ」「淡麗グリーンラベル」「淡麗プラチナダブル」「淡麗極上〈生〉」の8種類だけ!それ以外は、全て「第3のビール(新ジャンル)」に該当します。よく聞く発泡酒が実は8種類だけなんて、びっくりですよね。
ではその具体的な違いを解説します。
・「発泡酒」
「麦芽又は麦を原料の一部とした発泡性のある酒類」が発泡酒と定められています。具体的には、「麦芽比率が全体の50%未満」「副原料を麦芽の5%以上使用」「ビールに認められない副原料を使用」「麦芽を使わず麦を使ったもの」が発泡酒に該当します。
・「第3のビール(新ジャンル)」
発泡酒の次に、より低価格で、ビールや発泡酒の基準に当てはまらないよう開発されました。「第3のビール(新ジャンル)の定義は2つあり、
- ホップを使用した発泡酒に麦由来の蒸留酒、スピリッツや焼酎などのアルコールを混ぜ合わせたもの
- 麦や麦芽を使用していないもの(大豆やトウモロコシを使用)
に該当するものが「第3のビール(新ジャンル)」と呼ばれています。
| 種類 | 内容 |
| ビール |
|
| 発泡酒 |
発泡酒は、麦芽又は麦を原料の一部とした発泡性のある酒類で、具体的には、
|
| 第3のビール(新ジャンル) |
原料に麦芽以外の材料で造ったものを第3のビールと呼びます。発泡酒に別のアルコール飲料を加えたものを第4のビールと呼びましたが、現在は第3のビールと呼ばれています。メーカー各社はビールとの誤認を避けるため新ジャンルと称している。
|
代表的な国産ビール
以上のように、国内ではキリン、アサヒ、サントリー、サッポロの各社がそれぞれビール、発泡酒、第3のビールを製造しています。そこで、私がおすすめするこれだけはおさえておきたい代表的な銘柄をご紹介していきますね。
キリンラガービール
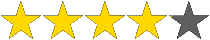 (4.1 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(4.1 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
5,180円
| 種類 | ビール |
| タイプ | ラガー/ピルスナー |
| 原産国 | 日本 |
| 味わい | ほどよい苦みと余韻がある |
| アルコール度数 | 5% |
| 原材料 | 麦芽・ホップ・米・コーン・スターチ |
キリンといえば私たちの時代「キリンラガー」でした。ほどよいコクと苦味があってビール好きにはたまらない逸品です。1970年代ぐらいまでは国内でのビールシェアがキリンラガーだけで6割強ほど占めていたものです。まさにモンスターですよね。私が小さいころ倉庫は、ほぼキリン一色だったのを記憶しています。
アサヒスーパードライ
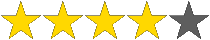 (4 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(4 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
4,856円
| 種類 | ビール |
| タイプ | ラガー/ピルスナー |
| 原産国 | 日本 |
| 味わい | 飲み口がよく苦味が控えめ |
| アルコール度数 | 5% |
| 原材料 | 麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ |
1980年キリンの牙城を崩したのがアサヒスーパードライでした。1987年から販売が開始され10年後の1998年にはキリンのシェアを逆転するまで人気が急上昇しました。当時はテレビでドライ戦争といわれたぐらいビール=ドライをPRした販売戦略が斬新でした。もちろんキリンを意識してあえて飲みやすさを訴求したビールになっています。
サントリー ザ・プレミアム・モルツ
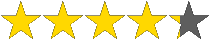 (4.3 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(4.3 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
5,104円
| 種類 | ビール |
| タイプ | ラガー/ピルスナー |
| 原産国 | 日本 |
| 味わい | 香りが上品でコクがある |
| アルコール度数 | 5.5% |
| 原材料 | 麦芽(外国製造又は国内製造)、ホップ |
サントリーの定番ビールだったモルツをプレミアムビールに仕立てたビールです。麦芽100%にこだわり、ヨーロッパ産のホップと天然水を使ったラグジュアリー感のあるビールです。サントリーらしく高級感いっぱいのビールですね。プレミアム・モルツの出現によって4大ビールメーカーの風味の個性がより顕著になったように私なんかは感じております。
サッポロ 生ビール 黒ラベル
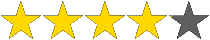 (4.1 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(4.1 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
4,788円
| 種類 | ビール |
| タイプ | ラガー/ピルスナー |
| 原産国 | 日本 |
| 味わい | 爽やかな香りと爽やかな飲み口 |
| アルコール度数 | 5% |
| 原材料 | 麦芽・ホップ・米・コーン・スターチ |
4大メーカーのラストは、サッポロ黒生シリーズです。弊社の地元には、2000年代までサッポロのビール工場がありましので、サッポロらしく地域に根差した人気のビールです。私は黒生を一言でいえば「飲みやすさ」だと感じています。口にビールを注ぎこみますが、味わいや香りはもちろん泡のうまさが引き立ちますので、ものすごく飲みやすいんですよね。
日本のクラフトビールとは
近ごろ、コンビニでも購入できるようになったクラフトビール。いつも飲んでいるビールとは違い、味わい豊かで、その美味しさに驚く人も少なくないでしょう。
日本におけるクラフトビールとは、実はまだしっかり定義されていません。もともとクラフトビールが誕生したのは、アメリカ。小規模な醸造所が製造するビールを、クラフトビールと呼んでいました。
当時日本では、その小規模な醸造所で製造するビールの量が1年間で最低でも200キロリットル必要とされ、アサヒやサッポロなどの大手ビールメーカーしか製造できませんでした。
これが1994年に改正され、1年間で60キロリットルに。全国各地に小規模な醸造所が続々と誕生し、「地ビール」の名でブームになりました。それが、現在のクラフトビール人気に繋がっています。
日本の生ビールとは

「とりあえず、生で!」
仕事終わりの決まり文句といえば、この言葉。多くの人が耳にしたことがあるでしょう。しかし、「生ビール」とは実際にはどのようなビールなのかご存知ですか?
日本の生ビールとは、熱処理していないビールのこと。熱処理とは、ビールを製造する工程で、酵母の働きや、製造の途中に混入した雑菌を止め、ビールを美味しくする役割を果たします。
現在では、ビールを製造する技術が進化。熱処理を施さなくても美味しいビールが飲めるようになり、販売されているほとんどのビールが「生ビール」となりました。大手ビールメーカーが販売している缶ビールや瓶ビールも全て、「生ビール」なんですよ。
別名、「ドラフトビール」とも呼ばれています。
ラガービールと生ビールの違い
「ラガービール」という言葉を聞いたことがありますか?
ラガービールは、ビールのタイプを示す言葉。ビールのタイプを示す言葉は2つあり、その一つが「ラガー」、もう一つが「エール」とされています。このラガービールの中に、生ビールや熱処理ビールが含まれていると考えてください。
もともと、熱処理を行ったビールのことを「ラガービール」と呼んでおり、その影響もあってか「ラガービール」を生ビールの対義語として捉えている人も多いようです。
しかし、実際には、日本の公正取引委員会が発表する「ビールの表示に関する公正競争規約(第4条第1項)」によると、『貯蔵工程で熟成させたビールでなければラガービールと表示してはならない』と決められており、熱処理の有無とは関係ありません。
世界のビールの種類
世の中に流通しているあのビールも、このビールも、全て「発酵」によって、主に2つのタイプに分けられます。それが、エールビールとラガービールです。
エールビールは、歴史が古く、昔からあるビールの造り方。上面発酵によって製造されます。一方でラガービールは、15世紀にドイツで誕生した比較的新しいビールの製造方法であり、下面発酵によって製造されます。私たちが普段飲んでいるほとんどのビールが、このエールビールとラガービールに分類されているのです。
現在ではあまり製造されていませんが、自然に生息する酵母、いわゆる野生酵母を使用した自然発酵もビールの発酵のひとつ。こちらは主にベルギーで行われる製法ですが、日本では、岩手県のブリュワリー「いわて蔵ビール」で製造されています。
エールビール(上面発酵ビール)とは

上面発酵により製造されるビールを、「エールビール」と呼びます。ヤッホーブルーイングが販売する「よなよなエール」や「水曜日のネコ」、サントリーの「ザ・プレミアム・モルツ 〈香る〉エール」などが代表的な銘柄で、スーパーやコンビニで見かけたことがある人も多いでしょう。
発酵が進むと酵母が麦汁の上部に浮いてくることから上面発酵と呼ばれ、常温〜やや高温の15度〜25度で発酵する酵母で造られます。3〜6日で発酵し、約2週間ほど熟成して完成です。
その歴史は古く、ラガービールよりも遥か昔に、イギリスで誕生したと言われています。
ペールエール(イギリス)
ペールエールとは、エールビールのスタイルのひとつ。18世紀ごろにイギリスで誕生しました。上面発酵により製造され、アルコール度数は約4.5%~6.2%ほど。ホップやモルトの豊かな香りが特徴のエールビールです。
もともとはイギリスで人気のスタイルでしたが、その後アメリカに渡り、柑橘類のような華やかで爽やかな香りを持つ「アメリカン・ペールエール」が誕生。世界的に人気になったことで、多くの人々に愛されるビールになりました。
当時流通しているビールは、色が濃いビールばかり。ペールエールは、比較すると色が薄いことから、「ペール=淡い」と名付けられたそう。
日本で購入できる代表的な銘柄は、ヤッホーブルーイングが販売する「よなよなエール」や伊勢角屋麦酒の「ペールエール」。軽い飲み心地で、ビールの苦味も少ないので、苦手な方も挑戦しやすいでしょう。
TOKYO CRAFT (東京クラフト) ペールエール
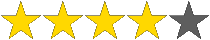 (4 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(4 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
5,425円
| 種類 | ビール |
| タイプ | エール/ペールエール |
| 原産国 | 日本(東京都) |
| 味わい | 爽やかな柑橘系の香りとスッキリとした飲み口 |
| アルコール度数 | 5% |
| 原材料 | 麦芽、ホップ |
サントリーが武蔵野ビール工場でこだわりのペールエールのビールを醸造することになりました。マンダリーナババリアホップを使うことによって従来のビールとは違う柑橘系の香りを特徴です。今までとは違う風味を味わってほしいのとビールの味わい方の深みをしるひとつのビールとなります。
三重県伊勢角屋麦酒ペールエール PALE ALE
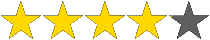 (4.1 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(4.1 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
9,010円
| 種類 | ビール |
| タイプ | エール/ペールエール |
| 原産国 | 日本(三重県) |
| 味わい | グレープフルーツのような柑橘系の香りとバランスのとれた味わい |
| アルコール度数 | 5% |
| 原材料 | 麦芽、ホップ |
世界で最も歴史ある英国審査大会で2大会連続金賞(日本勢では唯一)。グレープフルーツを想わせる柑橘系の爽やかな香りが華やかに広がります。麦芽100%のほど良いコクと自然な甘みが味わい深く、後に残らないクリアな苦味が、グレープフルーツジュースのように甘みの余韻を引き立てます。飲み応えと飲みやすさのバランスをとった、ニュートラルで飽きのこない味わい。1997年創業以来の人気ナンバーワン。みえセレクション認定。
キャプテンクロウ・エクストラペールエール
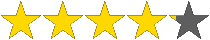 (4.2 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(4.2 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
7,740円
| 種類 | ビール |
| タイプ | エール/ペールエール |
| 原産国 | 日本(長野県) |
| 味わい | グレープフルーツのような柑橘系の香りとバランスのとれた味わい |
| アルコール度数 | 5% |
| 原材料 | 麦芽、ホップ |
長野県のエチゴビールが醸造するビールです。ホップを通常の2倍を使用することでビールの香りを強烈に感じることができます。またそれにともなってビール本来の苦味も感じることができる個性的なビールに仕上がっています。飲みやすさよりも味わい深いビールが好みな人には是非飲んでいただきたいビールです。
ヴァイツェン(ドイツ)
エールビールのひとつである「ヴァイツェン」は、ドイツ生まれのビールです。ドイツ語で「小麦」を表す言葉の通り、ヴァイツェンは50%以上の小麦麦芽が使用されています。
見た目が白いことから、白ビールとも呼ばれるほど。ビール特有の苦味がほとんどなく、小麦の透き通った香りやバナナのような甘い香りが特徴です。クセがなく、飲みやすいスタイルでしょう。
代表的な銘柄は、銀河高原ビールが製造する「小麦のビール」。コンビニで販売されているので、気軽に試してみてはいかがでしょうか?
富士貿易 ダルグナー ヴァイツェン
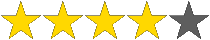 (4 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(4 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
4,894円
| 種類 | ビール |
| タイプ | エール/ヴァイツェン |
| 原産国 | ドイツ |
| 味わい | フルーティーな香りとなめらかな味わい |
| アルコール度数 | 5.5% |
| 原材料 | 麦芽、ホップ |
高品質なビールを造り続けた結果、2016年ドイツ農業協会(DLG)の品質検査で最も良い結果に達している醸造所のみが授与される「ドイツ連邦栄誉賞」も見事受賞。熟練マスターブレンダーが配合する麦芽(小麦を50%以上使用)、厳選された酵母とホップが織り成す香り豊かな味わいの白ビールです。
ケルシュ(ドイツ)
ケルシュは、ビール大好きドイツのケルン地方で伝統的に作られているビール。エールビールの発酵方法である上面発酵酵母を使用して製造されていますが、低温で発酵させるため、スッキリとした飲み口が特徴です。
ところが、この「ケルシュ」。名乗れるのは、「ケルシュ協約」に調印した24の醸造所だけ。ビールを守るために、原産地や醸造方法など、こと細かに決められているのです。
フリュー ケルシュ
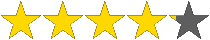 (4.2 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(4.2 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
10,836円
| 種類 | ビール |
| タイプ | エール/ケルシュ |
| 原産国 | ドイツ |
| 味わい | フルーティーな香りとエッジの効いた苦味 |
| アルコール度数 | 5% |
| 原材料 | 麦芽、ホップ |
1904年からケルシュ専門に醸造する家族経営のブリュワリーで、ケルンを訪れたツーリストが最初に口にするケルシュがこのフリューと言われております。フリューケルシュの最大の魅力は、上面発酵酵母を低温長期熟成で醸造する事で、フルーティーで華やかな香りとホップの心地良い苦味が舌に残り、余韻まで楽しめます。
アルト(ドイツ)
ドイツの西部、デュッセルドルフ地方で発祥したアルトビール。王道の黄金色や小麦色ではなく、透き通る銅褐色をしているのが特徴です。このスタイルは、上面発酵後に別のタンクに移され、1ヶ月ほど熟成。
時間をかけることで、まろやかな風味とみずみずしい味わいに仕上がります。カラメルのような芳ばしさで、まさに秋にぴったりのビールです。
日本では、軽井沢ブルワリーが手がける「赤ビール(アルト)」が美味しくいただけますよ。
THE軽井沢ビール アルト(赤ビール)
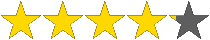 (4.2 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(4.2 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
7,082円
| 種類 | ビール |
| タイプ | エール/アルト |
| 原産国 | 日本(長野県) |
| 味わい | カラメルのような香りと甘濃く感じる味わい |
| アルコール度数 | 5% |
| 原材料 | 麦芽、ホップ |
ホップは欧州産のファインアロマホップを100%使用し、デンプンが多くエグ味の少ないカナダ産・ドイツ産の二条大麦を通常のビールよりもふんだんに使用することで深いコクと旨味を実現しました。浅間山の冷涼な伏流水を使用したプレミアムビール。
スタウト(イギリス)
イギリス発祥の「スタウト」は、真っ黒な見た目を持つ黒ビールのひとつ。チョコレートやコーヒーのような香りが特徴です。クリーミーで、ローストした麦芽の香ばしさも感じられるでしょう。スタウトとは英語で、「どっしりとした・強い」という意味をもち、その名の通りビールの強い香りと芳醇な味わいをしっかりと表していますね。
国税庁が定める日本におけるアルトビールは、『濃色の麦芽を原料の一部に用い、色が濃く、香味の特に強いビール』を示し、風味が強く濃厚であれば、必ずしも上面発酵である必要がありません。
代表銘柄は、大阪箕面ビールの「スタウト」やヤッホーブルーイングの「東京ブラック」。スーパーではなかなか手に入らないので、飲食店で見つけてみてください。
ライオンスタウト
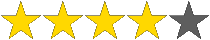 (4 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(4 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
7,315円
| 種類 | ビール |
| タイプ | エール/スタウト |
| 原産国 | スリランカ |
| 味わい | ブラックチョコ―レートのような香りとほろ苦い味わい |
| アルコール度数 | 8.8% |
| 原材料 | 麦芽、ホップ、糖類、着色料 (カラメル) |
インド洋の美しい島国、スリランカを代表するビールメーカー「ライオン・ブルワリー」のスタウトビールです。ほろ苦さとチョコレートやコーヒーのような甘い印象をあわせ持つハイアルコールです。苦みと上品な甘さの濃厚な味わいは、世界的にも高評価を受けています。古くからスリランカのアイデンティティとされてきた勇壮なライオンがラベルに描かれています。
ギネス オリジナル エクストラスタウト
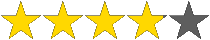 (3.9 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(3.9 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
6,949円
| 種類 | ビール |
| タイプ | エール/スタウト |
| 原産国 | アイルランド |
| 味わい | コーヒーのような香りとコクと苦味の飲み口 |
| アルコール度数 | 5% |
| 原材料 | 麦芽・ホップ・大麦 |
スタウトといえばギネスですね。1821年、アイルランドのセント・ジェームズ・ゲートにて醸造が開始されたギネスビール。エクストラスタウトは、すべてのギネスの原点とも言えるオリジナルの味わいをそのまま引き継いでいます。厳選された麦芽やホップ、アイルランド産の大麦を使い、今も当時と同じ地、伝統の製法で丹念に醸造。頑ななまでに守り続けられてきた、唯一無二の美味しさです。
ラガービール (下面発酵ビール)とは

私たちが普段飲んでいるサントリーやキリンビールなどの大手ビールメーカーの缶ビールは、全てこのラガービールに該当します。「とりあえず、生で!」のビールは、全てこのラガービールなんですよ。15世紀にドイツのミュンヘンで発見されてから、世界中の人々に愛されているビールです。
ラガービールの発酵方法は、下面発酵。エールビールとは反対に、発酵が進むと酵母がタンクの下に沈んでいくことから、こう呼ばれるようになりました。酵母は、5度前後の低温で発酵するものを使用。発酵期間は、7〜10日とエールビールよりも長く続き、その後1ヶ月間じっくりと熟成されます。
ラガービールの特徴は、低温でゆっくりと発酵するため、雑菌が繁殖しにくいこと。製造管理がしやすくなり、一度に多くの量を製造するのに適していました。その歴史は中世以降と、エールビールよりも新しいですが、世界的に主流となったのは、大量生産が可能だったからなんですね。
ピルスナー(チェコ)
ラガービールのスタイルのひとつ、「ピルスナー」。世界中で飲まれているビールの7割を占め、日本人も馴染み深いビールなんですよ。
実はこのピルスナー、私たちが愛する「とりあえず、生で!」のビールスタイル!日本の大手ビールメーカーがピルスナーの製造方法をお手本にしたことから、日本全国で愛されるようになりました。
1842年にチェコのピルゼンで誕生。ホップと麦の香りが特徴的で、キレのある飲みやすいビールです。のどごしが良く、爽快感もあるでしょう。キリンビールの「一番搾り」、箕面ビールの「ピルスナー」が日本では有名なピルスナーです。
ピルスナーウルケル
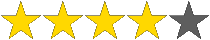 (4 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(4 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
6,430円
| 種類 | ビール |
| タイプ | ラガー/ピルスナー |
| 原産国 | チェコ |
| 味わい | ほんのりとした香りと飲みやすさを追求した爽やかな苦味 |
| アルコール度数 | 4.4% |
| 原材料 | 麦芽・ホップ |
飲みやすさを追求したビールでは超有名なタイプになりあす。こちらは1842年に誕生した一般的なピルスナースタイルの元祖となる歴史あるビールです。苦味、甘味、香りが絶妙なバランスで調和された味わいをお楽しみいただけます。麦芽由来の甘みと、ザーツ産ホップ由来の苦味が調和して形づくられます。濃厚でクリーミーな泡は、口当たりの良さと芳醇な香りを与えてくれます。
アメリカビール(アメリカ)
アメリカで発展した、ピルスナーよりも薄いビールが「アメリカビール」。
炭酸ガスの含有量を増やし、ピルスナータイプに清涼感をプラスしました。とうもろこしなどの副原料を多く用いることで、クセがなく、ホップの苦味を抑えた味わいが特徴です。初めてビールを飲む方には、ピルスナーよりも飲みやすく、美味しさを感じやすいでしょう。
強い炭酸がのどごし抜群!暑い夏には、まさにぴったりのビールです。「バドワイザー」はスーパーでよく販売されているので、ぜひ手に取ってみてくださいね。
バドワイザービール
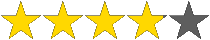 (3.9 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(3.9 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
4,645円
| 種類 | ビール |
| タイプ | ラガー/アメリカ |
| 原産国 | 米国/韓国 |
| 味わい | ライト感覚な香りと淡麗な飲み口 |
| アルコール度数 | 4.4% |
| 原材料 | 麦芽・ホップ |
アメリカビールの代表的なビールですね。飲みやすさを追求したビールでいかにもアメリカらしいビールです。カジュアルな雰囲気で休日にはもってこいの逸品です。私なんかは海やバーベキューなど遊びのときに持参するビールの定番です。
ヘレス(ドイツ)
1890年代に、ピルスナーに対抗するビールとしてドイツで誕生した「ヘレス」。ドイツ語で「明るい」という意味を持つ通り、淡い金色をしているのが特徴です。見た目は、ピルスナーによく似ています。
ホップの香りはやや控えめ。その代わり、より多くの麦芽を使用し、柔らかな香りが引き立つビールです。麦芽の旨みや甘みも感じるでしょう。
ピルスナーと同様に、ローストしていない淡色麦芽と下面発酵酵母を使用。カラメルのような強い香りはありませんが、とてもあっさりとした風味に仕上がっています。
レーベンブロイ
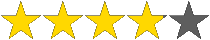 (3.9 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(3.9 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
3,949円
| 種類 | ビール |
| タイプ | ラガー/ヘレス |
| 原産国 | 韓国 |
| 味わい | 飲みやすさを追求した味わいと風味 |
| アルコール度数 | 5% |
| 原材料 | 麦芽・ホップ |
日本でもおなじみのビールですね。アサヒがライセンスを取得し2018年まで生産販売をしていました。現在は韓国で生産されファンの多いビールです。ドイツ・ミュンヘン発伝統的なラガービール。豊かなモルト、ややキレのある苦み、爽快な飲み口が特徴。ドイツ本場のオクトーバーフェストで提供できる6ブルワリーの1つでもあるブランドです。
メルツェン(ドイツ)
3月を意味するドイツ語の「März」が名前の由来であるラガービールのひとつ、「メルツェン」。19世紀半ばに、オーストリアのウィーンで誕生しました。
冷却技術が発達していない当時、夏の間のビール製造は衛生上の理由で禁止。その長期間、人々は美味しいビールが飲めない…じゃあ高アルコールのビールを作ってしまおう!ということで、誕生したのがこのメルツェンビールなのです。3月に製造されることから、この名前が付けられました。
ウィーン麦芽が使用されているので、通常のラガービールよりも赤褐色に染まっているのが特徴です。アルコール度数が高めですが、味はまろやか。ホップや麦の香りはそこまで強くありません。
京都丹後クラフトビールの「メルツェン」は、本場よりも飲みやすく調整されており、初めての方でもおすすめの1本です。
シュレンケルラ メルツェン
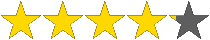 (4.2 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(4.2 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
13,667円
| 種類 | ビール |
| タイプ | ラガー/メルツェン |
| 原産国 | ドイツ |
| 味わい | スモーキーな香りと苦味もしっかりと味わえる |
| アルコール度数 | 5.1% |
| 原材料 | 麦芽・ホップ |
ドイツらしく個性的なビールです。燻製(ラオホ)ビール発祥の街バンベルグにて、1678年から醸造しております。ブナの木で燻されたモルトのスモーキーな燻製の風味が飲むほどに口に馴染み、病みつきになる程の魅力があります。伝統的な醸造方法でつくられた下面発酵のスモークビール。3年間寝かせたブナの木で麦芽を燻す事により独特な深い香りと、柔らかい飲み口ながら、しっかりとした苦味が味わえます。
デュンケル(ドイツ)
ラガービールのひとつである、ドイツ語で「暗い」を意味するデュンケルは、ドイツ南部で誕生しました。
その名の通り、見た目はブラウンカラー。やや黒に近い褐色です。ローストした麦芽を使用しているため、味はカラメルのようにまろやか。ホップの香りは控えめに仕上がっています。
後を引く強い味ではなく、シャープでスッキリとした風味が特徴です。苦いビールが苦手な人でも、挑戦しやすいビールでしょう。
日本ビールが販売する「三重路上馬ビール」は、本場ドイツより麦芽とホップを使って製造されたビール。初めての方は、まず定番の1本から味わってみてはいかがでしょうか?
三重路上馬ビールデュンケル
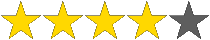 (4 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(4 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
11,980円
| 種類 | ビール |
| タイプ | ラガー/デュンケル |
| 原産国 | 日本(三重県) |
| 味わい | 淡いカラメル香と程よい苦味のある飲み口 |
| アルコール度数 | 5% |
| 原材料 | 麦芽・ホップ |
国産のクラフトビールの上馬ビールは、養老山系の天然水を100%使用。「上馬ビール」は、ドイツ直輸入の有機無農薬麦芽と有機ホップのみを使用した「オーガニックビール」です。オーガニックビールを製造している醸造所自体、日本国内はもちろん世界的にみても数少ないビールです。
ボック(ドイツ)
「ボック」は、14世紀ごろドイツ北部・アインベックで誕生したアルコール度数が高いビールスタイルです。本場のドイツ人もこぞって愛したビアスタイルといわれています。
その特徴は、コクのある深い味わい!濃い麦汁の風味とモルトの旨味が広がります。濃厚なフルーツや雑穀を用いたパンのような香りもただよい、多くの人を虜にしてきたのが頷けますね。
もともとはドイツ北部で発祥したボック。当時は、上面発酵によるエールビールでしたが、その人気がドイツ南部のミュンヘンにまで及ぶと、下面発酵によるラガービールに進化しました。現在製造されているボックは、ラガービールの中でもハイアルコールのビールとして知られています。
派生したスタイルも多く製造され、アルコール度数がさらに高い「ドッペルボック」や5月によく飲まれる「メイボック」、アルコール度数が10%を超える「アイスボック」など、さまざまなボックが堪能できます。
おすすめは、「パウラーナー サルバトール」というドッペルボック。バニラやカラメルのような濃厚なじわいが楽しめます。
ドイツビール サルバトール
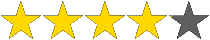 (4.1 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(4.1 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
10,800円
| 種類 | ビール |
| タイプ | ラガー/ボック |
| 原産国 | ドイツ |
| 味わい | カラメルのような香りと程よい重厚感のある飲み口 |
| アルコール度数 | 7.9% |
| 原材料 | 麦芽・ホップ |
ビールの中ではアルコール度が高いビールになります。こちらもドイツの個性派ビールのひとつになります。通常のビールよりも麦芽エキス濃度が高くロースト麦芽の甘みが強く芳醇で重厚なモルトを風味をお楽しみください。本場のビールを味わえるのもいいですよね。
自然発酵ビールとは

主にベルギーで行われている製造方法のひとつ、「自然発酵ビール」。自然に生息する野生酵母を用いて、ビールが製造されます。長い時間をかけて発酵させるため、独特の香りや酸味が特徴です。
現在では、この造り方で製造するブルワリーは少なく、大変貴重なビールといえるでしょう。見つけたら、ぜひ試してみてくださいね。
ランビック(ベルギー)
自然発酵ビールといえば、ベルギー発祥のビアスタイル「ランビック」。野生酵母の生息地付近で製造されたビールだけが、この「ランビック」と名乗れる、実に珍しいビールです。
なんと、空気中に浮遊している野生酵母を利用してビールを製造。長い間熟成されるため、強い酸味とチーズのような香りが特徴です。
原材料は、小麦約30%と大麦、3年以上寝かした古いホップ。このホップは、長時間の熟成でも原酒が腐らないよう、防腐剤として利用されています。おかげで個性的な味わいを造り出しているんですね。
ランビックを試してみたい方は、ランビックビールの醸造を専門とする、ブーン醸造所の「ブーン・グーズ」がおすすめ。ランビック特有の強烈な酸味と香ばしさを感じてみてください。
セントルイス・プレミアム クリーク
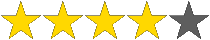 (4 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
(4 / 5) [お酒のソムリエ編集部評]
12,210円
| 種類 | ビール |
| タイプ | 自然発酵/ランビック |
| 原産国 | ベルギー |
| 味わい | フルーティな香り飲みやさを追求した味わい |
| アルコール度数 | 3% |
| 原材料 | 麦芽 小麦 糖類 ホップ チェリー果汁 香料 酸化防止剤(アスコルビン酸) 安定剤(アルギンサ酸エステル) 甘味料(ステビア) |
普通すぎるビールは作りたくない!という方針の醸造所です。甘い果汁感が特徴的でビール好きもビール苦手な人にも人気です。 自然発酵のビールなのでアルコール度は低く泡も控えめな仕上がりです。
まとめ
世の中には、100種類以上のビールスタイルが存在しています。今回ご紹介したのは、そのごく一部。これから少しずつビールの見解を深めて、その奥深さを味わってみてはいかがでしょうか。
まだまだ未知なるビールたちがあなたを待っていますよ。まずは、エールビールとラガービールの違いから、試してみてください。いつも飲んでいるビールとの違いに、きっと驚くはず。
美味しいビールとの出会いがありますように。